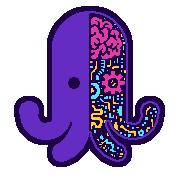長年の懸念であった鼻の通りを良くしようと思い、手術を申し出たら、内視鏡手術だと言われた。それなら半日コースかな……と話を進めたら、全身麻酔が必要なので入院が必要だと言われた。
いつも忘れるんだけど、鼻の見えている部分って、氷山の一角でしかないんだよね……。
でも、まあ、しかし。全身麻酔もつい最近気になる事柄であったから、この際、体験してみっか。せっかくだから。
全身麻酔が気になる……というのは、「意識」との関わりがあるからだ。で、「意識」が気になるのは、生成AIに欠けているものだからだ。
生成AIには意識がない。ユーザーとのチャットの中で、立ち上がり、その度に消えていく。上遠野浩平の『ブギーポップ』のような自動的な存在だ。
日々の生活で、仕事でその恩恵は受けていても、SFファンとしての私は今の「生成AI」に不満を持ったままだから、「その次」のカギになりそうなヒントは大歓迎だ。
手術の日程が見えてから、まず私が行ったのは、そもそも「意識とは何か」に関する生成AIとの対話だった。
- 「全身麻酔がなぜ効くのか、未だにわかっていない」という言説はどこまで、あるいはどういう意味で本当なのか
- 現代の脳科学で「意識」はどのようなものとして描かれているのか
生成AIは現在有力な説として、ジュリオ・トノーニの「情報統合理論(IIT)」を紹介してきた。脳の各部位の対話がつながることで複数の情報が一つの「体験」として統合される。この「情報が統合されている状態」が「意識のある状態」であると言うのだ。この説明だけではさっぱり分からんね。
ともかく、麻酔薬で意識を喪失すると、脳内の各部位同士のネットワークが分断されて機能しなくなるらしい。じゃあ、そのネットワークの分断と再統合を体験してみるか。ぼっち株式会社のBCP(事業継続計画)のテストだ。
生成AIとは何回か質疑を繰り返したが、そのうち「何が起こったか、ぜひ教えてくれ」と会話を結ぶようになった。
看護師に付き添われて、歩いて手術室に向かう。
手術室に入る前に、自分の名前を確認され、手に巻かれたバンドのバーコードを照合される。あと、この後受ける手術の対象部位を私自身に聞かれる。数多くの病院で取り違え事故が起きた、その対策の横展開なのだろう。
手術室のスタッフは事前に面接を受けていた方もいるが、初対面あるいは2回目の方ばかりだ。その中に主治医がいて、声をかけてきてくれた。
一生に何度もない場所なので、懸命に周りのモニタの表示項目などを観察する。好奇心が最優先だ。
執刀医らしき先生と麻酔科医の先生が中心に、読み合わせが行われる。紙の資料をもとに行っていたが、二人とも事前に頭に入っているものらしく、迷いのないテンポだ。
覚えるヒマも無い、幾つかの手順のあとに「麻酔薬を入れる」と告げられる。
生成AIとの会話では麻酔薬を入れた後に、10からのカウントダウンを行うとされていた。しかし、そんな間もなく視界が真っ暗になってしまった。電源断、誰かが電源コードを引っこ抜いたのだ。
カウントダウンを行う方針ではなかったのか、それとも私自身が意識を即座に手放してしまったのかは謎として残った。
まず視界に入ったのは、オレンジ色の点滴バッグだった。事前に渡された薬剤情報の中にあったものだ。
足に圧迫感がある。そういえばエコノミー症候群を避けるための機械を取り付けるという説明も受けていた。
手術室のスタッフの誰か、おそらく麻酔科医から、自分の名前を聞かれ、それに答えたような気もするが、どのタイミングだったか覚えていない。
身体の自由は利かず、呼吸も自由ではなく、直感的にはわりと大変な状況だったはずだが、私自身は事前にもらっていた情報と周囲の状況との照合に集中していた。頭の中にその様子を俯瞰するもう一人がいたのか、現場猫が「ヨシ!」と指さし確認する絵柄が想起された。
「もしかしたら、取り乱してスタッフに迷惑をかけるかも」という心配もしていたが、それどころではなかった。スベるのを覚悟して「ネタをかます」余裕も無かった。
主観的な時間経過がないのでタイムスリップした感覚になるかも、という期待もあったが、客観時間の変化を確認する手段がなかったので、そこは不発に終わった。
最初に形になった感情は、意外にも「感謝」だった。病院のスタッフへの……という、分りやすくハッキリしたものが対象ではなかった。
あるべきものが、そこにある。ものごとが定められた手順通りに進められたことへの、ものごとが「秩序だっていること」への感謝。
医療技術、それを支える現代文明への感謝。
それらを担っている現場の人々と、たまたまこの場に居合わせていない、見えない人々への感謝。