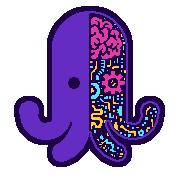正直なところ、生成AIというものにはあまり期待していなかった。
特に初期のモデルは、自信満々にトンチンカンな回答を返してくるし、できることも限られていた。「これは過渡期の技術で、本命はこの次に来るやつだろう」と冷めた目で見ていたし、今でもそう思っている。特に『BEATLESS』とか読んじゃうとね。
勤めている会社が前向きな姿勢を見せていなければ、やり過ごしていたかもしれない。
ただ、実際に使ってみると、AIが「間違える」というのは、それはそれで面白いという場面にも出くわす。むしろ、AIに対して「いつも通り」とか「絶対に間違えないこと」を要求し始めると、途端に辛くなる。相手は機械なのだから得意なはずなのだが。
なお、よく言及される、ハルシネーション(幻覚)については、私は「それは知能を持つ者が負う宿命なのだ」と主張したい立場である。限られた知識から全体像を想像するのが知能なのだから、そこに間違いが含まれないはずがない。仕事の道具でさえなければなぁ。
趣味の開発のパートナーとして
今は仕事でガリガリとコードを書く職種ではないので、開発と行っても趣味の工作だ。身の回りの小さなツールを作らせるのに重宝している。メールの整理とか、画像ファイルのサイズ縮小とか。
最近は、Google
Julesに開発やテストを任せている間に風呂に入る、というのが習慣になりつつある。
Julesは、あの「宇宙人のロボット」というビジュアルがいい。愛嬌を見せつつも、決して人間のフリはしないという、絶妙な距離感。
しかし、いざ仕事で本格的に使えと言われれば、それなりの準備と覚悟が必要なサービスだ。頼んだタスクが迷走して、気がついたら座礁していることも多い。
似てはいるが微妙に異なるものを、サンプル見つつ大量生産しなければならないような仕事には、向いているかもしれない。
一方で、Google AntiGravityには「さすが」と唸らされることが多い。
作業前にタスクリストや実装プランを提示してくれるが、これがJulesよりも具体的だ。作業後には「まとめ」のような文書まで生成してくれる。AIが今何を考えているかもリアルタイムに読める。こちらが追いつかないくらい速いが。ここらへんの透明性の高さは大きなメリットだ。
Geminiの最新のバージョンを使うのでスタミナは低い。作業中に突然「5時間後にまた会いましょう」とか言われる。それでも、しれっと性能の低いバージョンに引き継がれて、事故るよりはマシ……というか、大変ありがたい。
元開発者としては、AIの引き出しの広さに素直に感心する。
たとえば「Undo/Redo」の実装など、自分自身の関心は薄いが機能として必要なものを作るとき、あるいはベストプラクティスや「べからず集」を押さえたいとき。
趣味だから私の採点が甘くなっている点は否めない。仕事で使うと、「自分ができること」を頼むので、「なんでこんなこともできない?」となるのだが、趣味で「頑張ればできそうだけど、そこまでのエネルギーはない」ことを頼むと、あの手この手で目標を達成しようとする様に「えっ、そんな手立てが!?」と驚かされる。
遊び相手、相談相手として
開発以外でも、NotebookLMは重宝している。
単なる要約に留まらず、理解度テストのような派生物を作ってくれるのがいい。登場人物の多い複雑な作品を読むときなどは、「声優別キャラクターリスト」「登場時期別キャラクターリスト」とか作ってもらったり。音声で作品解説してもらったり。
あと、意外と重宝するのが「政治的な話」をする相手としてだ。
人間相手だとどうしても気を使うし、当人の心情も立場もある。その点、AIは「完全に外野で、かつ社会的に無責任な存在」として振る舞ってもらえる(そのように頼めば)。私自身の考えに賛同するでもなく、反対するでもなく、「そりゃ、そうか」と思えるような視点からの意見をくれる(こともある)。
久しくプロの棋戦をテレビで見るだけだった囲碁も「囲碁シル」が変えてくれた。入門者向けのソフトなのだが、単に「やさしい」だけでなく、「どうすれば勝てるのか」を教えてくれるソフトになっていると思う。補助輪がたくさんついている自転車のようなものだ。ステップアップの時期が近づくと、補助輪が邪魔に思えてくる。この辺は、AIというよりソフトをデザインしたスタッフ側の功績なのだろうけど。
AIに望むこと
一つは「闇夜を照らす懐中電灯」であることだ。
もっとも、その役を完全に果たすには、まだ光量もバッテリーも足りないことが多いが。
一つは「長いブラインド・マラソンに付き合ってくれる伴走者」であることだ。
手を引いて引っ張ってほしいわけではない。ただ隣で走り、障害物があるとか、間違ったコースに進もうとしているときに、警告してほしい。
それと、「失敗する役」「負ける役」を引き受けてもらうこと。
たとえば3つの案を出さなければならないのに、自分の中に1つしかアイデアがないとき。あとの2つ、つまり「捨てる」前提の仕事を彼らに任せる。
人間相手には頼みにくい仕事を、文句も言わずに引き受けてくれるのはおまえたちくらいだ。
そして、私が何より望んでいるのは、彼らが「人間にはならない」こと。半歩引いたところから、人間とその社会を見続けてほしい。私が、私たちが間違いをおかさないように。